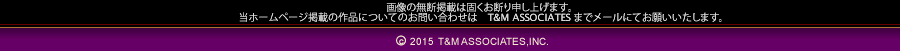![]()
飛鳥時代に大陸から伝えられた日本の製紙技術は平安時代に頂点に達し実用面とは別に文学・美術の世界に関わる分野でもさまざまな工夫がなされた。その一つが「料紙」である。
「料紙」は紙漉きの段階で加工するものと、漉き上げられた紙に加工するものの二種類に大別される。 前者には 打曇(うちぐもり)、羅文紙(らもんし)、飛雲(とび<も)などと呼ばれるものがあるが、現代ではその技術は殆ど廃れてしまっている。後者は 版木を用い雲母の粉で模様を刷る唐紙(とうし)、水の表面に松脂を用いて墨汁を拡げそれを紙に写し取る、墨流し、あるいは金、銀の砂子や野毛・切箔などで加工したり、金銀泥で直接描く方法もある。
また、さらに、これらの料紙を色々な方法で継いだ装飾紙などすべてが平安時代に完成されており、現在も装飾経や国宝「西本願寺本三十六人家集」「源氏物語絵巻」などにその姿を見ることが出来る。 その後衰退していた料紙の需要は桃山時代に復活し、その中で光悦が宗達の料紙を使った「書巻」や「嵯峨本」の木版雲母刷りの料紙などが生まれた。江戸中期以降は再び衰退し、明治維新を境に手漉和紙そのものが機械生産の洋紙に押されて実用性を失ってしまった。近年、その耐久性と芸術性から再評価されはじめ、各地に手漉和紙の後継者が生まれて来たが、料紙の分野は技術継承者がきわめて少ない。